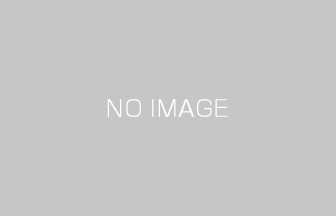楮から手すき和紙をつくる全工程のうち、取り組みやすい工程「③:削」「⑥:取」「⑦:叩」「⑧:漉」「➈搾」「⑩:干」を厳選。
初めての方でも安心して和紙ができるまでの一連の流れを体験できるプログラムです。さらに、和紙作りを通じて得た疲れを癒す、「こうぞハーブティー」のティータイムもご用意しています。手作りの和紙を楽しんだ後には、自然の恵みを感じながら、心温まるひとときをお楽しみいただけます。こうぞの香り豊かなハーブティーは、リラックス効果があり、創作の合間にピッタリです。
【削】(楮ひき/かずひき)
比企地域では楮のことを「かず」と呼びます。和紙の原料のこうぞの黒皮を白皮へと削る工程を「楮(かず)ひき」といいます。体験しやすいよう乾燥した楮を一夜、水につけて柔らかく準備をしていただいています。
一番外側は寒さ暑さから身を守るための部分「鬼皮(おにかわ)」。その下の緑色の部分が「あま皮」。あま皮を剥ぐと、和紙になる重要な部分「白皮(しろかわ)」が現れる。今回は、白皮なるまで丁寧に剥いでいきます。
【取】(ちりとり)
あく抜きのすんだ楮の皮から不要な部分を取り除きます。
繊維についた塵や不良な繊維を指先で丁寧に取り除きます。
POINT! この作業を丁寧にすることでより白い和紙になります。
【叩】(楮叩き/かずうち)
「楮打棒・木槌」で叩いて楮の繊維を叩きほぐし、綿のようになるまで、叩きほぐしていく工程です。
POINT! 繊維が細かくなるように手前に引きながら叩きます。
現在は、打解機・ビーターという機械を使っておこなわれていて、唯一機械化されている行程とのことでした。
ほぐした楮を、とろみのついた水に入れてかき混ぜ、専用の道具ですくいあげると、和紙の姿が見えてきます。
和紙っぽい、感動(笑)
【漉】(和紙漉き・流し漉き)
いよいよ和紙漉きの工程です!
漉舟(紙漉き槽)に水を張り、ほぐした楮とトロロアオイの粘液を混合し、「簀桁」(すげた)で一枚一枚漉きあげる。
先生に事前に紙料の入っていない透明な水を使って、丁寧に漉き方や捨て水のやり方を練習させて頂きました。
通常の体験でできるのは、この工程が多いですよね。今回は説明も含め、和紙ができるまでの、一連の流れを全て知ることのできる、めちゃくちゃプレミアムな体験です!
紙を漉くまでに、こんなに多くの工程が必要とは…
【干】(紙干し)
一枚一枚「干し板」に張って、天日に干しにする。
空気が入らないように丁寧に干していきます。自分ではうまく漉けたと思っていましたが、かどが…(笑)
職人さんは一枚一枚、手作業で同じ厚さの紙を漉いていくんですよ。和紙漉き以外にも多くの工程があり、和紙ができるまでに多くの時間がかかっていることを知ることができます。

お子さまや、紙漉きがはじめての方でも、とっても丁寧に教えてくれますよ。
紙漉きを通じて「日本の伝統」を感じてみませんか。この体験でしか味わえないこうぞハーブティーで心温まるひとときをお楽しみください。
体験で漉いた和紙は、後日送るか、乾くまで待って持ち帰るかを選べます。
| 開催日時 | 2024年10月~2025年4月末 9:30~12:30 約3時間 |
| 体験プログラム | 体験プログラム開始・体験の案内(工房集合9:20/9:30) 【削】(楮ひき) 【取】(ちりとり) 【叩】(楮叩き) 【漉】(和紙漉き・流し漉き) 休憩(和紙の原料「こうぞハーブティー」でティータイム) 【干】(紙干し) プログラム終了(12:30頃) |
| 体験料金 | おひとり様 6,820円(材料費込み) |
| 人 数 | 2名様(小学生以上)~4名様まで ※お申込みは原則2名様からとなります。1名様でお申込みの場合は2名様分の参加料金が発生いたします。参加人数入力時に「2名」をお選びください。 |
| 持ち物 | 汚れてもよい服装、エプロン、 |
| 申込期間 | ※準備等の都合上、希望日の10日前までにお申込みください。 |
| 場 所 | 埼玉県比企郡ときがわ町玉川地区(※お申込み後にメールで開催場所をお伝えします。) |
| アクセス | 🚴東武東上線「小川町」駅より約8㎞(レンタサイクルあり) 🚌「武蔵嵐山駅」よりイーグルバス「一ト市」下車徒歩5分 🚉JR八高線「明覚」駅より徒歩15分 |
| 駐車場 | あり(普通車2台~3台) |
※予約システムに遷移します。
【お客様によるプログラム契約の解除】
| 取 消 日 | 取 消 料 |
|---|---|
| 体験開催10日~6日前 | キャンセル料なし |
| 体験開催5日前 | 旅行代金の50% |
| 前日 | 旅行代金の100% |